
『ICHI』曽利文彦監督に学ぶ映画製作講義
9月30日(火)、秋葉原のデジタルハリウッド大学にて、曽利文彦監督が講師として招かれ、映像作家を目指す学生達の前で講義を行った。曽利監督は南カリフォルニア大学の映画学科に留学中、『タイタニック』のVFXスタッフに参加。帰国後、VFXスーパーバイザーとして『ケイゾク/映画-Beautiful Dreamer-』などを手がけ、2002年に『ピンポン』で監督デビュー。その後も『ベクシル -2077 日本鎖国-』など、既存の映像方式にとらわれない映像作家として活躍中だ。この日は、自身の新作『ICHI』(現在絶賛公開中)を教材にして、映像製作とは何かについて企画から完成に至るまで、段階ごとにじっくりと語ってくれた。
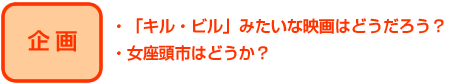

映画というものは、企画することから始まる。『ICHI』はまず最初に、『座頭市』という原作の映画化権を持つプロデューサー、中沢敏明氏のひらめきからスタートした。これは『キル・ビル』の影響も大きかったという。企画内容として、男性の座頭市のリメイクという形もあったが、これは以前北野武監督が作ったものがあったので、プロデューサーは趣を変えて「女座頭市」でやろうという形になった。
ならば監督は誰にしようか、というところで、曽利監督が選ばれた。曽利監督自身は「どうしてか私のところにお話が来まして」と謙遜する。中沢プロデューサーはマンガチックなB級風の映画を期待していたというが、曽利監督は勝新太郎の『座頭市』の大ファンであり、それをキワモノ的なものにしてしまうのは許しがたいことで、まっとうな時代劇として作ることを目指したという。
曽利監督は、「勝新太郎の『座頭市』をリメイクするとなると、北野武監督くらいの個性がなければ、よほど勇気があるか大馬鹿野郎でなければできる仕事ではない」と語るが、今回は「女座頭市」ということで、これならば更地から再構築できると考えた。しかも座頭市は目が見えなくて剣に強い。作り手として、これほど魅力的な登場人物はいない。それはチャレンジしがいのある仕事だった。
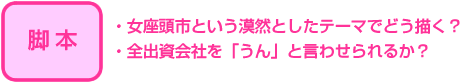

企画が立つと、次は脚本の執筆。今回はただ漠然と「女座頭市」というテーマがあるだけで、ストーリーはどういうものにするのか、まったく決まっていない。だからゼロから書いていかなければならいのだが、自分の思い描いている世界をそのまま脚本に書いたところで、それがOKをもらえるとは限らない。
というのも、映画を作るにはお金が必要で、そのためには出資会社にお金を出してもらわなければならず、出資会社は脚本を見てからゴー・サインを出すことになっているからだ。脚本はすべての出資会社が「うん」と言わなければOKにならない。出資している会社が多ければ多いほど、書き直しも多くなる。曽利監督は何度プロットを書き直したかわからないという。『ICHI』の場合、ジェネオンやTBSが出資しているが、それぞれの会社が求めているものを作らなければいけない。ジェネオンはDVDの会社なので、当然DVDになって売れる作品を要求してくる。DVD向けの映画と映画館向けの映画とでは作り方も違ってくるので、ここにも悩まされる。TBSはテレビ局なので、当然テレビで放送できる作品を要求してくる。テレビ向けの映画と映画館向けの映画とでは、やはり作り方が違い、ここもまた悩まされる。ここをすり合わせていくのは難しい話である。
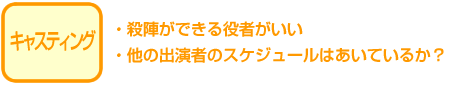

続いて、女座頭市役を誰がやるのか?という話だが、曽利監督は「生身で殺陣のできる人を使いたかった」と語る。一切ワイヤーやCGのごまかしはなしだ。女性の場合いくらやっても女性の動きになるので、ある程度それを超えていってもらわないといけないのだが、ちょうど監督は『白夜行』の綾瀬はるかの演技を見て彼女に通じるものを見出し、監督は一番に彼女の名前をあげたという。
しかし問題もある。綾瀬はるかはお芝居については申し分ないが、殺陣ができるかどうかはわからなかった。そこで、彼女に会って早々、黒澤明監督の映画で殺陣を教えていた先生に指導を受けさせることにすると、先生から「彼女は行けますよ」と太鼓判を押してもらったそうで、すぐに出演が決まったという。
注意してもらわなければいけないこともある。出演者には誰にでもスケジュールがあり、スケジュールを撮影の都合に合わせることは、思いのほか難しいことを知っておかなければならない。特に『ICHI』のように人気スターが何人も出演する映画となると、多忙な役者達にピンポイントで映画に出てもらうことはなかなかOKをもらえるものではなく、どうしても交渉を諦めなければならないことだってある。監督は「お芝居としては台本の順番に撮りたいが、順撮りは高級なことで、我々の世界にそんな贅沢な話は許されない。一番困るのは、後半にしかでない役者さんのスケジュールの都合で、後半から撮らざるを得なかったとき。後半を先に撮ってしまうと、前半も後半に合わせなくて撮らなければならない。後半を撮ったときに何か忘れてしまったら辻褄が合わなかくなる」と、事の重大さを強調する。
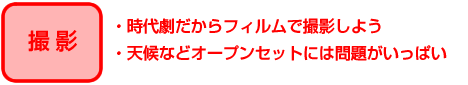

曽利監督は、撮影現場をデジタルカメラで撮った映像とフィルムカメラによる実際の映画の映像を比較してみせた。デジタルカメラで見る映像は、何か軽くて、とても映画とは思えず、おかしささえ感じさせたが、実際の映画の映像の方は、スタイリッシュな映像になっていて生徒達を驚かせた。今回の撮影はすべてフィルムカメラで撮影しているが、監督は「フィルムは、ある種ひとつのスタイルを持っている。普通の時代劇をデジタルで撮ると誰が見てもちょっと変だなと思う。時代劇はフィルムの方がしっくりくる」と説明する。
夜のシーンでは、日が暮れてから撮影を開始し、夜明けに終わるという、昼夜が逆転した日々を強いられたという。しかし曽利監督は「映画撮影中は、独特のアドレナリンが出て、寝なくても大丈夫なんですよ」と語る。また、雨には相当泣かされたという。雨が降れば撮影はできないし、雨がやんでも、たまった水を布で拭き取らなければならなかったといい、舞台裏は相当過酷だったようだ。
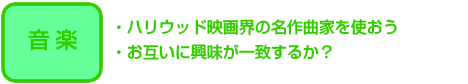
『ICHI』の音楽は、日本人ではなく、リサ・ジェラルドという外国人の女性が担当している。彼女はハリウッド映画界で活躍している人で、『グラディエーター』の音楽などで知られる。曽利監督は、ハリウッド映画界の音楽家に日本の時代劇の音楽を作らせてみたら面白いと考えた。幸い、その気持ちはリサ自身の気持ちと一致した。監督はとにかくラッキーだったと語るが、それは彼女にとってもチャレンジといえるものだった。
リサ・ジェラルドは、田舎の農場の一軒家に住んでいる人で、隣の家に行くのにも車が必要というくらいで、そこに最先端の音楽スタジオを持っているという。仕事のやりとりはすべてeメールだそうで、監督はeメールでひとつひとつ打ち合わせをして仕事を進めたという。『グラディエーター』も『ICHI』も史劇という点では共通しており、監督は撮影中、『グラディエーター』の曲がずっと頭の中で鳴っていたという。


撮影の後は、撮った映像をいかに加工するか。曽利監督は、時代劇を作るときに、自分の得意分野であるデジタルを打ち出すのは、キワモノ的な印象を与えてしまいそうで、とにかく表向きはデジタルというものをすべて消し去りたかったと語る。『マトリックス』のようなものを一切やらず、目指すところは黒澤明監督が撮るものを今の時代にやることだった。よって、この映画には「CGでござい!」というシーンはない。しかし、実はわからないところで大量にCGを投下しているという。全カットが1000くらいあって(曽利監督にしてはカット数は少なめ)、その半分はデジタルで加工しているというから、ある意味これはデジタルまみれの映画だが、監督は「デジタルだからこそできることもある。これだけのアクションを入れて60日間で撮影ができたのは、デジタルの力だ。デジタルで革新的に映画製作が変わった」と胸を張る。
最後に監督は「日本映画は製作費が100億円あっても作れない。なぜなら100億円を使ったスタッフがいないので、使い方が誰もわからないからです。ノウハウがなければお金があっても使えない。そういう意味ではステップアップしていかなければならない。その点、CGは素晴らしいツールだと思う。CGであれば役者を連れてこなくても表現できるから面白いことができる。逆に言えば、CGなら何でもできるから言い訳がきかない。言い訳がきかないところで自分の実力を試すというのもいいかもしれない。スタートは人それぞれ。自分がやりたいと思うことを極めていけばいいと思う」と生徒達にアドバイスし、濃厚な内容の講義は1時間で終了。その後、生徒達が曽利監督にサインをせがむ微笑ましい風景も見られた。





