大ヒット映画『のだめカンタービレ』ができるまで
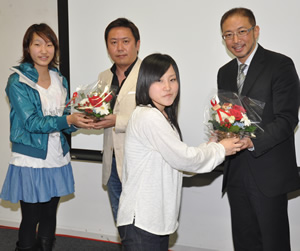

5月20日(木)、秋葉原のデジタルハリウッド大学にて、大ヒット映画『のだめカンタービレ 最終楽章 前・後編』の武内英樹総監督と若松央樹プロデューサーを迎えての公開講座が行われた。
『のだめカンタービレ』は漫画が原作。テレビドラマ化されて話題を呼び、現在劇場版が大ヒット公開中だ。この講座では、『のだめカンタービレ』がどういう経緯でテレビドラマ化され、映画が完成したのかが語られた。
まずドラマ化について。これは色々な局が動いて、争奪戦が繰り広げられたのだという。原作にはポリシーがあって、ドラマ化の一番の条件として、「クラシックを真摯に受け止めてやっていただきたい」ということだった。結果として、フジテレビが月9というフラッグシップ枠で勝ち取った。若松Pは「火9くらいがテイスト的に合ってると思ったのですが、こういうのを月9でやったらいいかと思いました。月9でごみ溜めに住んでいる人が主役というのは冒険でした」と振り返った。
若松Pと武内監督はちょうどそのとき『電車男』を作っていて、武内監督は秋葉原のメイド喫茶に通ってオタクの生態を調べていたところだった。武内監督は最初「クラシック?」と言ってオタクとは真逆のモチーフを出されて首を傾げたという。原作を読んでもいまいち良さがわからず、主人公は変な奇声を発するし、よく白目になるし、これをどう表現したらいいのか戸惑った。その後、音大を取材し、音大には実際に変わった人が多いことを知り、コントラバスをやっている女の悲哀だとかそういうところに細かいツボがあると知り、そういう探求心から原作にのめりこんでいったという。
キャスティングについて若松Pは「決まっていなかったので、その時期、大物は仕事が埋まっていて、新しい人を集めようと話に乗ってきた人をごそっと集めた感じ」と話した。駆け出し俳優の寄せ集めだったが、今では皆トップスターに成長している。これが初主演となる玉木宏も最初のきっかけはルックスからだったという。玉木は白目をむくのがうまくて、他のキャストに細かく教えていたそうで、本人が一番やりたがっていたことも明かした。
武内監督は「どうせカツラをかぶせちゃうから意外と誰でもいけると思ったのですが、ドイツ人を使って字幕で見ても面白くないから、いっそ日本人にやらせた方が面白いと思いました」と付け加えた。
スタッフは『電車男』をやっていたメンバーが馬が合うということで、そのまま『のだめ』の撮影に引き継がれた。そのため『のだめ』は『電車男』の影響がかなり色濃く表れているという。その中で、若松Pはキャラクター、音楽、ギャグの3要素を核として作り込んでいったと語る。最近はCGをみても誰も驚かなくなったことから、武内監督はその逆手をとって、「何てチープなんだ」と思わせることにした。のだめを殴るシーンも玉木宏に人形を殴ってもらうことでギャグにキレが増した。
スペシャルをやったときから映画化する気はまんまんだったという武内監督だが、クランクイン初日は災難にも遭った。ロケ地のプラハに入ったとき、浴槽にお湯をためている間、少しうたた寝をしていたら、ホテルの8階から1階まで水浸しにしてしまったそうだ。目が覚めたら池の中にベッドが浮いているような幻想的な風景になっていて、ホテルの廊下はまるで川。これを見た瞬間、武内監督は「この映画はもうダメだ」と嫌な予感がしたという。
武内監督はまずホールが決まらなければ撮影が始まらないということで、ホール探しのためにヨーロッパ各地をかけ巡ったという。すでにスペシャルで割と大きなホールを使っていたので、映画ではさらに大きなホールを使う必要があったため、交渉もねばった。毎日飛行機に乗っていたので気圧と疲労で奥歯がポロッと抜けたとも。最終的にチェコのナンバー1のホールで撮影することになったが、実際、金さえ出せばどこでも撮れるとのことで、ものすごい額がかかっているという。しかし、シネスコの横長画面、フィルムの質感において、オーケストラの映像もプラハの風景も画面の締まりがよくなり、得たものは大きかった。
若松Pは、海外ロケについて、「お金を節約するのは、滞在日数を減らすことが一番手っ取り早いので、出演者たちには地獄を見てもらいました」と話した。42日間の撮影で5時間の映画を撮影。スタッフ・キャストは不眠不休の日々が続いた。
実は劇中登場する楽団は本物。楽団員に芝居をやらせているが、武内監督は「やっぱり音楽が大事なので、音楽の素人に音楽をやらせるわけにはいかなかったのです。彼らの芝居もいい味を出すんですよ」と振り返っていた。
その中で玉木宏は指揮をしているわけだが、映画になるとドラマの頃よりもだいぶうまくなったという。武内監督は玉木を演出するのではなく、本物の指揮者に芝居をつけて、それを玉木に見てもらうようにしていた。
オーケストラのシーンでは何台もカメラを同時に回し、編集マンにつないでもらって、たたき台を作ってもらってから、そこから練り込んで行く形が取られた。また、玉木にはナレーションもやってもらっている。武内監督は「やっぱりクラシックは敷居が高いんですよ。そこに玉木宏のナレーションが入ることで曲の意味がわかるんです」と説明。短い撮影期間で玉木には忙しい思いをさせたが、武内監督自身はこの撮影を通してクラシックが大好きになったという。
サウンドトラックの録音は、ロンドンのアビイ・ロード・スタジオで行われた。「ビートルズも『ロード・オブ・ザ・リング』もここで録音していて、こんなにすごいところで録音して本当にいいのだろうか」という気持ちだったという。クラシックが主役ともいえる本作だが、武内監督は、最も思い入れのあるシーンは、チャイコフスキーの『1812年』のシーンだと語った。原作では『ウィリアム・テル』が使われていたが、映画は他の曲がいいと思って悩んでいたところ、『1812年』と出会い、弱者が勝つというこの曲に描かれているテーマにもひかれたという。大砲が楽器として使われている曲だが、映画ではじっくりと曲の中の世界が浮かんでくるように演出。まさにクライマックスといえるシーンはこうして誕生した。
なお、デジタルハリウッド大学では、時々こうして国内外の映画人を招いて公開講座を行っている。(取材・澤田英繁)
2010/05/24 0:43



